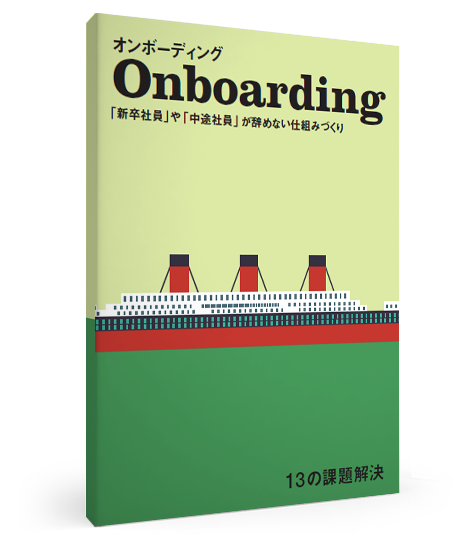オンボーディング Onboarding 「新卒社員」や「中途社員」が辞めない仕組みづくり
『オンボーディング』とは、新入社員をスムーズに社内に溶け込ませ、パフォーマンスを上げさせるための一連の仕組みづくりを言います。この冊子ではHR先進国であるアメリカ企業の事例も踏まえ、人材育成のための最新のメソッドを解説。
オンボーディングの具体的な取り組み方をご紹介しています。
![]() テレワーク
テレワーク
公開日:2020.5.26

安倍晋三内閣総理大臣が2020年4月7日(火)、新型コロナウイルス拡大防止のため、外出自粛などの要請を徹底する「緊急事態宣言」を発令しました。この発令をきっかけに、テレワークの導入に踏み切った企業も多かったのではないでしょうか。
実際に、4月上旬からテレワークを実施している企業の割合は39.1%と、同年1月時点の18.4%から2倍以上に増えたことが、NTTデータ経営研究所の調査でわかりました。
つまり、今回の在宅勤務要請(※)が出たタイミングで「急遽」テレワークに切り替えた企業の方が、前もってテレワークの制度を整え実施していた企業よりも、多いと言えるでしょう。そんな準備不足のまま始まった、慣れないテレワークの中で、さまざまな社員間のトラブルが発生しています。
今回は、慣れないテレワークによって引き起こされる社員間のトラブルに対して、人事部ができることは何かを一緒に考えていきましょう。
※在宅勤務要請:https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200413004/20200413004.html
初めてテレワークを導入する企業には、社内にモデルケースにできる前例がありません。また、今回のように急にテレワークを実施した場合、問題が起きた際には、その都度解決策を模索していくことになります。
しかし、テレワークを行う社員の勤務環境(今回の場合は自宅の環境)はさまざまなので、いろんな課題、解決方法が出てくることが予測されます。人事担当者が社員一人ひとりの課題に対応してしまったら、かなりの労力が必要になります。柔軟に対応しすぎて、労務管理ができないとなってしまっては本末転倒…。
そうならないためにも、まず初めに、十分に雇用側と社員が話し合うことで基本ルールを作り、書面に残すことが大切です。以下に、基本ルールの例をご紹介します。
▼基本ルール例
・環境整備
会社PCの貸与、自宅ネット環境、電話対応方法 など
・ルールの明確化
勤怠管理、会社PCの使用ルール、ウイルスソフトの導入、セキュリティ対策、業務報告方法、
連絡手段、労働時間 など
そもそもテレワークは、社員の働き方を柔軟にするために適用される制度です。したがって、最初に決めたルールをそのまま運用するのではなく、何か不具合があったらその都度話し合って変更していくべきでしょう。
しかし、柔軟に対応しすぎて、労務上の管理ができなくなってしまっては本末転倒です。社員から意見を聞き出せる機会を設けましょう。一人ひとりの社員と向き合いつつも、解決できた課題を、会社全体のルールとすり合わせていくことで業務効率化を図りましょう。
そして、そのルールは社内にも周知徹底させ、変更点があれば、その都度新たに書面に残し、再度全社員に共有しましょう。
テレワークでは、「特定の人だけを特別扱いしない」ことも大切です。全社員がルールを理解できるように、社内ポータルサイトやHRシステムを活用するなど、共有方法には工夫が必要です。
「誰かのためのテレワーク」にならないために、雇用側は社員と話し合い、制度をバージョンアップさせることでトラブルを防ぎましょう。
出勤していれば他愛のない話などで会話で社員同士もコミュニケーションを取ることができます。
しかし、テレワークはslackやチャットワークなどのオンラインコミュニケーションツールや、zoom、HangoutsMeetなどのオンライン会議システムを使った画面上での会話に限られます。
また、リアルタイムの連絡も難しく、事務的な会話だけになってしまうなどのコミュニケーション上の課題もあります。そうなると、社員は孤独感を持ってしまい、それが長期化すると、チームや会社に対する帰属意識が薄まる危険性があります。
また、社内であれば雑談の中で情報共有ができていましたが、テレワークの場合は意識していないと情報が偏ってしまう可能性もあります。情報のブラックボックス化が起き、自分の知らない情報があると知った時「仲間外れになってしまった」と、社員の孤独感を深める結果になるでしょう。
そうならないために、人事部発信でコミュニケーションの機会を設け、意識して雑談を増やしていきましょう。下記は、オンラインでもできるコミュニケーションの方法です。
▼コミュニケーション例
例1 SNSへの反応
SNSのメンバーの書き込みに「いいね」やコメントをするなど、情報共有に対するアクションをとることで、テレワーク中の社員もオンライン上で発言をしやすくなります。
Point1
このように社員は、自分の思いや感じた内容を素直に伝えられることで、安心して何でも言い合えるチームだと感じる「心理的安全性」を確保することができます。そうすれば、テレワーク中でも、先輩社員や上司になんでも相談や質問ができるので、ストレスなくスムーズに業務を行うことができます。
例2 始業時間、終業時間を共有する
始業・終業をチャットなどで共有しあうことで、「みんなで一緒に働いている」という帰属意識を高めることができます。
Point2
自分が終業する前に、まだ残業しているメンバーがいたら「何かお手伝いできることはありますか?」と聞き、協力することで、お互いの信頼関係の構築にもつながります。
例3 定例ミーティングを各部署オンライン会議システムで実施
オンライン会議システムなどを利用して、顔を見て話す機会を定期的に作りましょう。今まで毎日顔をあわせて仕事をしてきた仲間なので、オンラインであっても顔を見ればその人の気持ちがなんとなくでもわかるはずです。
Point3
特に人事担当者や部下を持つ上司は社員の表情や言動からその気持ちを読み取る必要があります。例えば、社員の表情が暗かったり、発言に元気がなかったりする場合は「最近不安なことない?」と質問して、社員の悩みを聞いてあげましょう。
例4 社内交流会をオンラインで実施
最近はWeb会議ツールを使って参加者と一緒にお酒を飲む「オンライン飲み会」が流行っています。ぜひ試してみてください。オンライン飲み会では、私服だったりといつもとは違う雰囲気になるので、心の距離も近づくかもしれません。
Point4
社員同士、対面でのコミュニケーションが少なくなった分、「最近仕事は順調?」「休日は家でなにしているの?」などの些細な質問からでも良いでしょう。また話の内容が極力明るい話題、楽しい話題になるように意識してみましょう。
テレワークによって、コミュニケーションの頻度が少なくなると、社員は孤独を感じ、つい人を攻撃したり、ネガティブな感情に働くことがあります。そのため、社員間でコミュニケーション上のトラブルも起きやすくなるのです。
社員が同じ情報量を持つこと、テレワークという物理的な距離を埋めるための意識的な雑談を増やすことで、コミュニケーション頻度をあげていきましょう。
今回、新型コロナウイルスの影響で「やむなく」テレワークに切り替えた企業が多いのが現状です。
そもそもテレワークという言葉自体、ここ数年の働き方改革の中で聞かれるようになりました。
しかし、仕事は出社して行うのが当たり前という環境の中で働いてきた社員が大半を占めます。
なので今回、やむなくテレワークに切り替えた企業の社員にとって、「テレワーク大歓迎!」とはならないのが現状です。一方、比較的若い世代の社員は、新しい働き方に柔軟に対応することができます。
そうすると、上司は「テレワーク推奨ではないが、(コロナウイルスによる影響だから)仕方ない」ととらえます。しかし、部下は「自由な働き方ができるほうがいいから、テレワークで働きたい」と考えます。
つまり、上司と部下の間でテレワークに対する考え方に差が生まれてしまうのです。この差から、上司と部下の心の距離が開いてしまう恐れがあります。
また、上司から部下に「テレワークにしてもいいよ」と伝えることで、テレワークをしている部下は、余計な気を使うことになり、テレワークに関する課題や解決策を部下から提案しづらい環境を作ってしまいます。
次のようなことを人事部から発信することで、テレワークをポジティブな制度にすることが可能です。
・テレワークを会社全体が推奨している
・テレワークに関する課題や解決策をどんどん提案してほしい
以下は、テレワークをポジティブな制度にするためのポイントです。
▼テレワークをポジティブな制度にするには?
・テレワークに関する課題、提案を受け付ける意見箱を社内掲示板やHRシステムなどに設置
・社員からの提案に対し、会社としての正式な回答を出していく
・課題について再度検討し、制度をバージョンアップさせていく
人事ができることについてお伝えしましたが、そもそも、上司と部下が日頃からコミュニケーションを取っていれば、テレワークに対する考え方に差が生まれただけで、上司と部下の心の距離が開いてしまうなんてことは起きません。
テレワークになるとより密なコミュニケーションが必要になりますが、今までのコミュニケーションを見直すきっかけにもなります。テレワークをよりポジティブな制度にするために、全社的にテレワークを奨励し、人事担当者や上司からは社員が抱えている悩みを吸い上げることがポイントととなります。
仕事をするうえで起こりうる全てのトラブルは、「社員同士のコミュニケーション不足」であるといえるでしょう。実は、このトラブルは、出社して仕事をしている状況でも起こりえるものなのです。テレワークに限ったことではありません。日頃から社員同士の信頼関係が構築されていればスムーズに解決することができます。
とはいえ、テレワークによる物理的な距離が作り出す「社員同士のコミュニケーション不足」という課題もあります。
今回のテレワークの導入は、これまでの社員同士の信頼関係をより一層高める機会になるでしょう。そのためには人事や上司が積極的に社員から意見を集め、それを発信することが求められています。
「テレワークはコロナウイルスが落ち着くまでの期間限定だから…」と消極的に考え、こうした課題に何も手をつけていない企業もあるのではないでしょうか?
「コロナが起きる前の世界には戻れない」と宣言する専門家も多くいます。つまり、テレワークを含めた、働き方の変化に柔軟に対応していく必要があるのです。
今から、テレワークでもできる社員間トラブルの解決方法を身につけていきましょう。
この記事を書いた人