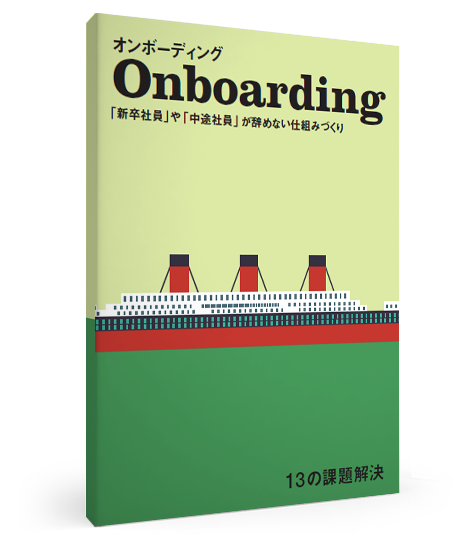オンボーディング Onboarding 「新卒社員」や「中途社員」が辞めない仕組みづくり
『オンボーディング』とは、新入社員をスムーズに社内に溶け込ませ、パフォーマンスを上げさせるための一連の仕組みづくりを言います。この冊子ではHR先進国であるアメリカ企業の事例も踏まえ、人材育成のための最新のメソッドを解説。
オンボーディングの具体的な取り組み方をご紹介しています。
 人事異動・配置
人事異動・配置
公開日:2021.3.25

欠勤が続くような問題のある従業員がいると、退職させるべきかどうか迷います。しかし無理に退職させるとトラブルに発展してしまうことも。そこで、欠勤の続く従業員を退職させる際にトラブルを避けるポイントについてまとめました。

どういった事例で会社が悩むことがあるのか紹介します。
無断欠勤者に頭を抱える会社は多いです。ただし、どのようなケースで無断欠勤とみなされるのか企業によって異なります。そのため、正当な理由と認められなかった場合は事前に連絡していても無断欠勤にされることがあるのです。あるいは、所定の権限者に対して連絡していなかった場合にも、欠勤の条件を満たさず無断欠勤として扱われます。
無断欠勤を続け、その後会社に来なくなったり、従業員が音信不通になったりする事例も多いです。これはとても対処に困ります。電話やメール、手紙などあらゆる手段を講じても連絡が取れなくなるのです。
無断欠勤が続き、連絡もつかないケースになると、その従業員を退職させるかどうか検討する必要があります。会社としては、できるだけ退職は避けたいもの。なぜなら退職に伴って欠員を補充しなくてはならない場合があり、これまでその従業員にかけたコストも無駄になるのです。それでも、いつまでも無断欠勤を許すわけにはいかないため、最終的には強硬手段に出る必要があるのです。
無断欠勤に対処する際には、法律や規則に従うことが大切です。無断欠勤したからといって、即、従業員を退職させられるわけではありません。もし、法律や規則に違反する形で退職させてしまうと、後で訴えられるリスクがあります。適切な手続きを経て退職させましょう。
無断欠勤者を退職させようとする際に生じるさまざまなトラブルについて紹介します。
従業員は法律や規則によって守られている存在です。使用者が自由に解雇してしまうと、従業員にさまざまな不利益が生じるため、守られているのです。そのため、無理に退職させようとすると不当解雇になってしまうことも。従業員側が訴えた場合、処分が適当であるかどうかを裁判所が判断し、違法と判断された際には慰謝料を支払う必要が出てきます。違法な処分には、懲役または罰金が科されるという罰則もあるため注意しましょう。
すべての無断欠勤者を処分できるわけではありません。欠勤の原因によっては、労働者の権利が守られるからです。会社に責任が問われることもあります。
無断欠勤をしたものを処分するには、証拠を用意する必要があります。無断欠勤の証拠が残っていないと、後で訴えられた場合に不利になるのです。タイムカードや出勤簿などできちんと出勤の記録を残しておけば、裁判で認められる証拠となります。証拠がなくて会社側が敗訴した事例もあるため気をつけましょう。
従業員を解雇する場合の手続きは、会社がメンバーに通知を出すことです。そして、メンバーが通知をきちんと受け取る必要があります。通知を出さずに手続きを進めるのは違法となります。
仮にメンバーが受取拒否したとしても、通知を送ったという事実があれば問題ありません。そのため、書面を送るのはとても重要です。
無断欠勤している従業員を退職させるための方法を紹介します。
無断欠勤者をいきなり処分すると、トラブルになるリスクがあります。そこで、退職勧奨するという方法があります。退職勧奨とは、会社を辞めるように勧めることです。この方法では、会社を退職するかどうか決めるのはあくまでも従業員です。上手く説得できれば、お互い納得して退職という結論を出すことができるでしょう。ただし、相手を脅したり騙したりして退職を促すのは違法であり、訴えられる可能性があります。
規則に無断欠勤した場合の記述があるならば、退職の手続きを進められます。「14日間無断欠勤を続けた場合は最終の日をもって自然退職したものとする」といった記述を含めておきます。法律に違反しない内容であれば、ルールは認められます。
懲戒処分とは、企業が従業員に対して行う制裁のこと。懲戒処分には減給や降格などさまざまなものがあり、最も厳しいものが懲戒解雇です。
一般的に懲戒処分はとてもハードルが高いものです。有効性を認められるには、会社に実害が生じるレベルでないと認められません。それは滅多にないことであり、十分な理由のない処分は違法となります。たとえ規則に記載があっても、そのまま適用できるとは限りません。
無断欠勤した従業員が失踪して行方不明となっているケースがあります。この場合は、解雇通知を渡せず、手続きを進めることができません。このようなケースでは、簡易裁判所に公示送達の手続きをします。
公示送達とは、相手方の居所がわからない場合や相手方が不明の場合などに、法的に送達したものとするための手続きです。簡易裁判所から公示送達の許可をもらえば、会社の意思表示が従業員に到達した事実が保証されます。無断欠勤した従業員が行方不明になった場合には、簡易裁判所を頼りましょう。

これから無断欠勤した従業員を退職させるまえに考えておきたい点について紹介します。
無断欠勤したからといって従業員の処分が常に正当であるという保証はありません。病気や職場環境などが原因となっている場合は対策を取る義務があります。詳細を調べずに処分すると、後で裁判を起こされるケースがあるため注意しましょう。
無断欠勤の原因がメンバーに責任のないものであれば、会社として全力でサポートするべきです。復帰支援を行うことを検討しましょう。休職して心身を休ませる、セクハラやパワハラをした上司を処分する、部署異動を行うなどの対策が考えられます。復帰して以前のように働けるようになるための応援をしましょう。従業員のためにも会社のためにも、できれば処分せずに問題を解決するのが理想的です。
ただし、復職の見込みがあるかどうか、事前にしっかりと検討すべきです。見込みのない従業員に復職支援をし続けても残念ながら可能性は低いでしょう。また、メンバーが復職を希望しないこともあります。意思を確認しておくことは大事です。
会社で働くのが困難なメンバーには、テレワークを提案することもできます。在宅勤務であれば、職場のメンバーと顔を合わせず一人で仕事が可能です。オフィスにいることに抵抗のあるメンバーにはテレワークの提案は魅力的。コロナによってテレワークが一般的になり、自治体の補助を受けることもでき、導入しやすくなっています。
無断欠勤が続いたメンバーの処分では、退職金の支給が問題になりやすいです。従業員側に責任があったとしても、退職金が発生することがあるのです。基本的に、すべては規則や規定に従うことになるため、事前にチェックしておきましょう。記載がない場合は退職金が発生する可能性があります。
従業員の処分は法律が関わる問題であり、素人が判断するのはなかなか難しいもの。誤った対処をしてしまえば、会社が不利な立場に追い込まれることになります。もし、対処に困った場合には法律の専門家を頼りましょう。弁護士に相談すれば、それぞれの状況を詳しく聞き出して、法的に正しい対処法について助言を得られます。必要な手続きのサポートを弁護士に頼むことも可能です。
ポイントは労働問題に詳しい弁護士を頼ること。これまでの実績が豊富で、実際に会社の問題を解決してきた実績があることが理想的です。弁護士事務所へ相談すれば、該当する弁護士を紹介してくれます。
あるいは事前に顧問弁護士を雇っておくという方法もあるでしょう。顧問弁護士がいれば、何かあったときにすぐ意見を聞けます。
そもそも無断欠勤者を出さないための対策を考えておくことは大切です。職場環境に問題があれば、これからも次々と無断欠勤が発生してしまうかもしれません。労働環境に問題がないか、人材配置は適切か、パワハラやセクハラなどの人間関係の問題が起きていないのかなど調査してみましょう。問題が見つかったならば、早急に対処することで無断欠勤を未然に防げます。定期的にアンケートや面談を実施するとよいです。
アンケートでは従業員の心理的な状況を探れます。アンケートの結果を専門的に分析すれば、どの従業員が問題を抱えているか把握可能。自社で行うだけではなくアンケートを外注して解決する方法もあります。
面談では、1on1ミーティングのような施策が有効です。1on1ミーティングによって上司と部下が定期的に一対一で面談する機会を設ければ、常に各メンバーの現状を把握することができます。それによって少しの変化も見逃さずにスムーズな対処が可能です。
コロナによってテレワークが増えています。テレワークであっても、無断欠勤のリスクがあるのです。在宅でやる気がなくなって、欠勤やさぼりが増えることもあります。もし、テレワークを導入するならば、準備をすることが大切。テレワークだからこそ、メンバーの管理はとても重要です。
欠勤の続く従業員が出た場合、適切な対処をしないと会社にとって大きなリスクとなります。法律や就業規則を守り、適切な対応をしていきましょう。退職を促すだけでなく、。欠勤の原因によっては、従業員が復帰できるようるサポートも必要。トラブルを避けて適切な対処ができるように注意しなくてはなりません。
この記事を書いた人